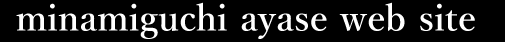才能がある人ほどやめてしまう
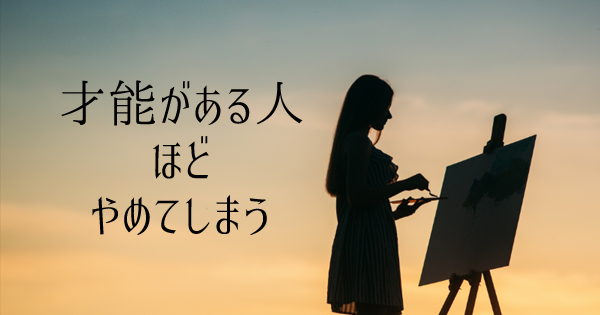
これは私が二十代の頃、とても絵の上手い同僚が言った言葉です。
この言葉は、絵を描くことを仕事にしてまだ4年目の私にとって魅力的すぎました。 そして、その日から二十年以上、私に付きまとい続けました。
いつでも創作活動をやめられる免罪符となってしまったのです。
私にとっての創作活動
絵を描くということは、勉強も運動も苦手、自分の思いを伝えるのも下手な私にとって、 物心ついた頃からの唯一の表現方法でした。描く以外のことでは稼いでいけないとわかっていたので、 必死に自分を売り込んでそれを仕事にしました。
仕事なのでクライアントの求めるものを目指して作ります。 二十年あまり、喜んでもらうことにやりがいを感じて楽しく働いていたと思います。
創作活動をやめた理由
その後、次男の出産を期に私は退職、二歳差で三男が産まれたことでさらに復帰は遠のきました。まわりのお母さんたちが復帰するのを見ていて焦る気持ちはあるのに、 私はそのまま、創作活動に戻ることをしませんでした。 例の免罪符が、ここぞとばかりに顔を出したからです。
私には才能がある。だからやめた。
正直、創作活動は辛いです。 求められるものを作るのは楽しかったと書きましたが、私にとっては辛いことのほうが多かったのです。 他にできることがないから続けていただけで。
実際のところ私は天才なんかじゃないわけですが、 同じように「創作活動をやめた」経験から、彼らがやめた理由は知ることになりました。
限界が見えてしまったのです。
自分の限界であったり、活動の未来に対する限界であったり、 もっと大きな、存在そのものに対する限界であったり、人によって様々。
生意気にも限界を見ていた私は、それでも習慣化した「創作」からは離れられません。 理由を見つけては何かを作っていました。だけど本気にはなれない。
何故なら「これは創作活動ではなくただの趣味だ」と、常に言い訳をしていたからです。
私を変えたのは
その日は突然やってきました。切っ掛けをくれたのは、私が創作活動をやめた表向きの理由にしていた息子たちです。 正確には、息子たちの「創作活動」です。
まず次男。
画用紙で漫画雑誌を作り始めました。
断面はガタガタだしホチキス留めですが、ちゃんと表紙とタイトルがある。 数名の作家(自作自演)が描いた漫画が掲載されていて、画用紙で作った車の付録まで付いていました。
家の廊下には自作の宣伝ポスターまで貼って。 ブームが去ったあとは、著名な作家の本が並ぶ本棚に、大切に、当たり前のように収めていました。
弟(三男)という固定ファンまで付いている。 ファンが喜んでいるのを、満足そうに眺めている作者。
これはあきらかに「ただの趣味」じゃありませんよね。
そして長男。
時を同じくして、小説投稿サイトで連載を始めました。
親が言うのもなんですが、冷めた16歳なのです。 だから将来を見据えたことにしか興味がないと思っていた。 書くことが好きなんて知らなかった。 というか、本人もわかっていなかったようです。
長男は「待っていてくれる人がいるからやめられない」と言いました。 この子の口からそんな言葉が出るなんて・・・まあともかく。
ファンを思って書いている時点で、これも「ただの趣味」じゃありませんよね。
創作活動、再開
私は「ただの趣味」を甘く見ていたようです。趣味なら適当にやれるのかと言われれば、そんなことはまったくないわけで。 創作活動との境界線なんて、あってないようなもの。 だったらもう、面倒な感情に飲み込まれて始められないくらいなら、考えるより先に始めてしまえばいい。
才能がある人ほどやめるのだとしても、そのやめた人の創作活動は止まってしまった。 だけど、私の目の前にある「創作活動」は始まったばかりで、これからもきっと続いていく。
それなのに、私が「創作活動をやめた」ということは、 この子たちの創作活動をもいつか終わりが来ると言っているようなもの。
それはちょっと、許しがたい!
再開した私の創作活動は絵だけではありません。それも子どもに教わったことです。 やったことなくて当たり前。やってみなきゃわからない。 それでも思い切って始めれば、誰かは受け入れてくれる。
こうして物語を書いたことのないデザイナーが、いきなり長編小説を書き始めるという暴挙に出たのでした。
子どもたちが「創作活動は楽しいもの」だと思っていけるように、 今度こそ私は楽しむことを忘れず、創作活動と向き合っていきたいです。
2021/8/14 南口綾瀬
◀ memo